眼科
眼科
概要
医師紹介
外来診療担当表
科の方針
- 眼の健康を守るため、常に学ぶことを怠らず、適切な医療を患者さんに提供できるように努めます。
- 丁寧な診療を心がけ、検査や手術に当たっては、十分な説明を行い、安心して眼科医療を受けていただけるよう努めます。
- 地域の医療機関と緊密な連携を保ち、セカンドオピニオンにも対応します。
- 他の診療科と常に連携を保ち、全身的なケアに努めます。
- 眼科専門医を志す、若い医師の育成を行います。

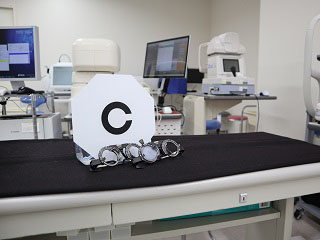

診療内容
概要
- 眼科専門医6名、専門医志向医2名の計8名で診療を行っています(2023年4月現在)。
- 眼科全般に関する診療に加え、白内障、網膜硝子体疾患、緑内障、斜視弱視などの小児眼科疾患に重点をおいています。
白内障
- 白内障は眼の中のレンズ(水晶体)が濁って、ものがだぶって見える、まぶしい、かすむなどの症状を引き起こす病気です。
- 加齢が主な原因ですが、その他に糖尿病など、全身の病気に合併するものなどもあります。
- 手術は、眼球に2〜3ミリの切開を加え、水晶体の中身を砕いて吸い出し、プラスチック製のレンズを移植する方法(超音波乳化吸引術と眼内レンズ挿入術の同時手術)が一般的で、日本では年間100万件以上の手術が行われています。
- 当科では患者さんのご希望と、全身状態などを併せて考慮し、日帰り手術と入院手術のいずれかで行っています。通常は局所麻酔での手術ですが、全身麻酔での手術も可能です。
- 日帰り手術は外来センター病院内の日帰り手術センターで行っており、手術日、翌日、翌々日の3日間の通院が必要です。
- 入院手術は片眼について、1泊2日ないし2泊3日で行っております。入院日に手術を行います。1泊2日の場合は退院後、翌日外来受診が必要です。
- 白内障手術のご予約は1~4か月先となります。手術待ちの期間は担当医により異なりますので、詳しくは眼科外来までお問い合わせください。
- 多焦点眼内レンズを使用する白内障手術を行っています(選定療養)。
網膜硝子体疾患
主に以下の疾患について、検査、治療を行っています。
- 糖尿病網膜症:糖尿病による3大合併症の一つで、眼の中に出血したり、眼球の裏側の膜(網膜)が腫れたり(糖尿病黄斑浮腫)、網膜がはがれたり(牽引性網膜剥離)して視力が低下します。
当科では当院の糖尿病センターと連携し、全身管理のもと、網膜レーザー光凝固術、硝子体手術、抗VEGF薬硝子体注射などの治療を積極的に行っています。 - 網膜剥離:網膜に孔(網膜円孔)や裂け目(網膜裂孔)ができて、網膜が眼球の壁からはがれてしまう病気です。放置すると失明します。網膜復位術(バックル手術)、硝子体手術を行っています。
- 加齢黄斑変性:加齢を主な原因として網膜の中心(黄斑)の網膜下に水や出血が溜まり、視力が低下する病気です。
抗VEGF薬の硝子体注射を主に行っています。 - 網膜静脈閉塞症:動脈硬化により、網膜の静脈が詰まり、あふれ出た血液や水分などにより黄斑網膜が腫れ、視力が低下する病気です。
抗VEGF薬の硝子体注射や網膜レーザー光凝固術を行います。 - 黄斑上膜:黄斑網膜の表面に薄い膜が形成され、ものがゆがんで見えたり、視力が低下する病気です。軽度の場合は経過をみますが、重度のものには硝子体手術を行います。
- 黄斑円孔:黄斑の中央に孔ができて視力が低下する、中高年の女性に多い病気です。早めの硝子体手術で視力を回復することができます。
緑内障
緑内障は、視神経が障害され、視野(見える範囲)が狭くなったり部分的に見えなくなったりする病気です。実際に視野障害が起きていても、無意識のうちに両方の目で補い合い、見えなくなった部分を周囲がカバーするため、自分では気付かないことが多く、また視野欠損が中心に及ばない限り視力は低下しないので、病気の発見が遅れることも少なくありません。
日本緑内障学会が2000年9月から2001年10月にかけて行った大規模疫学調査では、40歳以上の日本人の20人に1人が緑内障にかかっていると報告され、現在中途失明原因の第1位です。早期に発見し、治療を開始して病気の進行を抑えることが大切です。
当院では、手術を中心とした緑内障診療を行っております。
担当医:成田亜希子、野田拓志
2022年の緑内障手術内訳
観血的手術
| トラベクレクトミー | 170件 |
| 低侵襲緑内障手術 | 188件 |
| ニードリング | 28件 |
| 濾過胞再建術 | 8件 |
| ロングチューブシャント手術 | 4件 |
| 隅角癒着解離術 | 2件 |
| その他 | 19件 |
| 合計 | 419件 |
レーザー手術
| 選択的レーザー線維柱帯形成術 | 26件 |
| レーザー虹彩切開術 | 13件 |
| マイクロパルスレーザー毛様体光凝固術 | 33件 |
| 合計 | 72件 |
手術症例数
2022年の手術症例数は1,660件でした(レーザー手術を除く)。
| 白内障手術 | 1,040件 |
| 緑内障手術 | 419件 |
| 網膜硝子体手術 | 182件 |
| その他 | 19件 |
論文(雑誌・単行本)
| タイトル | 執筆者/共同執筆者 | 掲載誌/出版社 | 巻・号/ページ/掲載年 |
|---|---|---|---|
| 自家層状強膜グラフトを用いて融解強膜弁を被覆した濾過胞再建術の1例 | 滝澤早織、杉原佳恵、桝田悠喜、瀬口次郎、成田亜希子 | あたらしい眼科/(株)メディカル葵出版 | 40(08) 1097~1102 2023年 |
| 総説 緑内障治療の現状 | 成田亜希子 | 岡山済生会総合病院雑誌 | 53 1-6 2021年 |
| Corynebacterium ocular infection after Baerveldt glaucoma implant surgery: treatment involving immediate tube withdrawal and temporary subconjunctival tube placement: a case report. | Mitsui N, Sugihara K, Seguchi J, Chihara E, Morizane Y, Narita A | BMC Ophthalmol | 18;21(1):368 2021年 |
| Evaluation of blood-filling patterns in schlemm canal for trabectome surgery | Sugihara K, Narita A, Mitsui N, Okuda S, Seguchi J, Morizane Y | Journal of Glaucoma | 29 1101-1105 2020年 |
| 緑内障: 診断と治療の最新情報ーMIGSの予後は予測可能か | 成田亜希子 | あたらしい眼科/(株)メディカル葵出版 | 37 1253-1264 2020年 |
| 分層黄斑円孔に対する硝子体術後の視力と中心窩網膜厚の検討 | 光井奈瑠香、瀬口次郎、杉原佳恵、奥田聖瞳、成田亜希子 | 臨床眼科 | 74 601-608 2020年 |
| Impact of cataract surgery on filtering bleb morphology identified via swept-source 3-dimensional anterior segment optical coherence tomography | Narita A Morizane Y, Miyake T, Sugihara K, Ishikawa T, Seguchi J, Shiraga F | Journal of Glaucoma | 28 433-439 2019年 |
| 胎生血管系遺残に起因する硝子体出血術後の視野障害 | 杉原佳恵、瀬口次郎、成田亜希子、能祖美樹 | 眼科手術 | 32(3) 404-407 2019年 |
| 両眼性の重篤な視力障害を発症したMPO-ANCA陽性肥厚性硬膜炎の1例 | 杉原佳恵 瀬口次郎、成田亜希子、能祖美樹、藤田計行、上野明子、山村昌弘 | 臨床眼科 | 72(8) 1135-1140 2018年 |
| Characteristics of early filtering blebs that predict successful trabeculectomy identified via three-dimensional anterior segment optical coherence tomography | Narita A Morizane Y, Miyake T, Seguchi J, Baba T, Shiraga F | British Journal of Ophthalmology | 102(6) 796-801 2018年 |
| Characteristics of successful filtering blebs at 1 year after trabeculectomy using swept-source three-dimensional anterior segment optical coherence tomography | Narita A Morizane Y, Miyake T, Seguchi J, Baba T, Shiraga F | Japanese Journal of Ophthalmology | 61(3) 253-259 2017年 |
| トラベクトームを用いた流出路再建術の短期術後成績と術後合併症 | 清水壮洋 成田亜希子、三宅智恵、秋元悦子、能祖美樹、瀬口次郎 | 岡山済生会総合病院雑誌 | 49 44-44 2017年 |
| 特発性傍乳頭脈絡膜新生血管膜にベバシズマブ 硝子体注射を施行した1例 | 清水壮洋 熊瀬文明、秋元悦子、成田亜希子、能祖美樹、 瀬口次郎 | 臨床眼科 | 70 1645-1651 2016年 |
| Successful resolution of stromal keratitis and uveitis using canakinumab in a patient with chronic infantile neurologic, cutaneous, and articular syndrome: a case study | Hirano K, Seguchi J, Yamamura M, Narita A, Okanobu H, Nishikomori R, Heike T, Hosokawa M, Morizane Y, Shiraga F | Journal of Ophthalmic Inflammation and Infection | DOI:1186/s12348-015-0065-9 2015 |
| Paecilomyces lilacinus-induced scleritis following bleb-associated endophthalmitis after trabeculectomy | Narita A, Seguchi J, Shiraga F | Acta Medica Okayama. | 69, 313-318 2015年 |
講演・学会発表
| 演題 | 発表者/共同研究者 | 学会/講演会名 | 開催 |
|---|---|---|---|
| 「緑内障」から目を守るために | 成田亜希子 | 京山公民館出張セミナー | 2023年12月 岡山 |
| トラベクレクトミー術前の抗炎症治療:術後成績と濾過胞形態への影響 | 赤塚陸、三宅智恵、滝澤早織、野田拓志、秋元悦子、瀬口次郎、成田亜希子 | 第68回岡山大学眼科学教室同門会ならびに学術講演会 | 2023年11月 岡山 |
| 網膜細動脈瘤破裂に伴う黄斑下出血移動術前後の網膜感度にHenle線維層出血が与える影響 | 赤塚陸、木村修平、土居真一郎、細川海音、塩出雄亮、的場亮、神崎勇希、森田哲郎、金永圭祐、森實祐基 | 第77回日本臨床眼科学会 | 2023年10月 東京 |
| 濾過胞眼における白内障手術後の眼圧変化の予測因子 | 底押桃香 | SAISEIKAI ×SENJU GLAUCOMA SEMINAR | 2023年11月9日 岡山 |
| トラベクレクトミー術前の抗炎症治療 | 赤塚陸 | SAISEIKAI ×SENJU GLAUCOMA SEMINAR | 2023年11月9日 岡山 |
| トラベクレクトミーが不成功となったときの次の手は | 滝澤早織 | SAISEIKAI ×SENJU GLAUCOMA SEMINAR | 2023年11月9日 岡山 |
| 濾過胞を有する眼における白内障手術後の眼圧変化に影響を与える因子の検討 | 底押桃香、三宅智恵、滝澤早織、野田拓志、赤塚陸、秋元悦子、瀬口次郎、成田亜希子 | 第34回日本緑内障学会 | 2023年9月9日 東京 |
| Characteristics of blebs that predict intraocular pressure change after cataract surgery identified via anterior segment optical coherence tomography | Akiko Narita, Tomoe Miyake, Momoka Sokooshi, Kae Sugihara, Yuki Masuda,Saori Takizawa,Jiro Seguchi, Yuki Morizane | 10th World Glaucoma Congress 2023 | 2023年6月30日 ローマ |
| Factors that predict intraocular pressure change after phacoemulsification in trabeculectomized eyes | Tomoe Miyake, Yuki Masuda,Momoka Sokooshi, Kae Sugihara, Saori Takizawa, Jiro Seguchi,Yuki Morizane, Akiko Narita | 10th World Glaucoma Congress 2023 | 2023年6月28日 ローマ |
| 緑内障手術アップデート | 成田亜希子 | ヴィアトリス製薬社内研修会 | 2023年5月16日 岡山 |
| 黄斑上膜の視力機能障害の術後経過について | 桝田悠喜、瀬口次郎、滝澤早織、杉原佳恵、成田亜希子 | 第46回日本眼科手術学会学術総会 | 2023年1月 東京 |
| 当院のトラベクレクトミー -術前管理- | 成田亜希子 | SAISEIKAI ×SENJU GLAUCOMA SEMINAR | 2022年11月 岡山 |
| 当院のトラベクレクトミー -術後管理と成績- | 杉原佳恵 | SAISEIKAI ×SENJU GLAUCOMA SEMINAR | 2022年11月 岡山 |
| デンマークからの留学生 | 桝田悠喜 | SAISEIKAI ×SENJU GLAUCOMA SEMINAR | 2022年11月 岡山 |
| 当院で行っているMIGS | 滝澤早織 | SAISEIKAI ×SENJU GLAUCOMA SEMINAR | 2022年11月 岡山 |
| マイトマイシンC併用濾過胞再建術の術後成績 | 杉原佳恵、滝澤早織、桝田悠喜、瀬口次郎、成田亜希子 | 第76回日本臨床眼科学会 | 2022年10月 東京 |
| 自家層状強膜グラフトを用いて融解強膜弁を被覆した濾過胞再建術の1例 | 滝澤早織、杉原佳恵、桝田悠喜、瀬口次郎、成田亜希子 | 第33回日本緑内障学会 | 2022年9月 横浜 |
| マイトマイシンCと濾過胞内ヒーロンVⓇ注入を併用したニードリングの成績 | 杉原佳恵、桝田 悠喜、滝澤早織、瀬口次郎、成田亜希子 | 第33回日本緑内障学会 | 2022年9月 横浜 |
| Evaluation of bleb morphology using three-dimensional anterior segment optical coherence tomography before surgical bleb revision following failed trabeculectomy | Kae Sugihara, Akiko Narita, Saori Takizawa, Yuki Masuda, Jiro Seguchi | 6th Asia-Pacific Glaucoma Congress | 2022年8月 クアラルンプール Web発表 |
| 当院におけるトラベクレクトミー術後5年の治療成績 | 杉原 佳恵 | 西部勤務医会 | 2022年7月 岡山 |
| 「緑内障」について知っておくべきこと | 成田亜希子 | 女性の健康週間 県民公開講座 人生100年時代、見える目で豊かな時間を | 2022年3月13日 岡山 |
| 緑内障手術の現状と展望 | 成田亜希子 | 第2回西讃眼科ゼミナール | 2022年3月5日 香川県丸亀市 Web講演 |
| 緑内障手術の現状と展望 | 成田亜希子 | SENJU Instruction WEB Seminar | 2021年11月17日 岡山 |
| 緑内障に対するロングチューブシャント手術の術後成績 | 桝田悠喜、杉原佳恵、有安奏、瀬口次郎、成田亜希子 | 第66回岡大眼科学教室学術講演会 | 2021年11月6日 岡山 |
| Evaluation of Blood-filling Patterns in Schlemm Canal for Trabectome Surgery. J.Glaucoma 2020 | 杉原佳恵 | 第66回岡山大学医学部眼科学教室同門会学術奨励賞(奥田賞)受賞講演 | 2021年11月6日 岡山 |
| 濾過胞再建術前の濾過胞形態と術後成績との関連についての検討 | 杉原佳恵、成田亜希子、光井奈瑠香、有安奏、桝田悠喜、瀬口次郎 | 第75回日本臨床眼科学会 | 2021年10月28日 福岡 |
| 保存強膜による強膜弁被覆とチューブシャント手術の併施が奏功した再発性房水漏出症例 | 有安奏、成田亜希子、杉原佳恵、光井奈瑠香、桝田悠喜、瀬口次郎 | 第75回日本臨床眼科学会 | 2021年10月28日 福岡 |
| Triple compression sutureによる結膜縫合が有用であった線維柱帯切除術の2例 | 桝田悠喜、成田亜希子、杉原佳恵、光井奈瑠香、有安奏、瀬口次郎 | 第75回日本臨床眼科学会 | 2021年10月28日 福岡 |
| 未治療の正常眼圧緑内障に対する選択的レーザー線維柱帯形成術の短期成績 | 杉原佳恵、成田亜希子、光井奈瑠香、有安奏、桝田悠喜、瀬口次郎 | 第32回日本緑内障学会 | 2021年9月11日 京都 |
| Evaluation of filtering blebs following surgical bleb revision after failed trabeculectomy via anterior segment optical coherence tomography | Sugihara K, Narita, A, Mitsui N, Seguchi J | 9th World Glaucoma Congress | 2021年6月 Web開催 |
| 最近SLTを始めて思うこと | 杉原佳恵 | 第125回日本眼科学会総会モーニングセミナー6 エレックスSLTセミナーvol.11 | 2021年4月 大阪 Web講演 |
| バルベルト緑内障インプラントを用いたロングチューブシャント手術 | 成田亜希子 | Johonson & Johnson VISION Surgical Seminar in 岡山 | 2021年3月 岡山 Web講演 |
| 当院での緑内障手術の現状と術後管理 | 成田亜希子 | 病診連携の会 Webセミナー | 2021年2月25日 岡山 Web講演 |
| 再考! 選択的レーザー線維柱帯形成術の位置づけ | 杉原佳恵 | 病診連携の会 Webセミナー | 2021年2月25日 岡山 Web講演 |
| 緑内障手術パラダイムシフト | 成田亜希子 | 第13回広島臨床眼科セミナー | 2020年11月 広島 |
| 当院でのSLT使用経験について | 杉原佳恵 | エレックスSLTユーザーミーティング | 2020年10月 九州エリア Web発表 |
| Clinical evaluation of blood-filling patterns in schlemm's canal for trabectome surgery | Sugihara K, Narita A, Mitsui N, Okuda S, Ishikawa T, Noso M, Seguchi J | 10th International Congress on Glaucoma Surgery | 2020年2月 ロンドン |
| Association between morphological changes in filtering blebs and intraocular pressure increase after phacoemulsification | Narita A, Miyake T , Sugihara K, Mitsui N, Okuda S, Ishikawa T, Seguchi J | 10th International Congress on Glaucoma Surgery | 2020年2月 ロンドン |
| Treatment of endophthalmitis after baerveldt glaucoma implant surgery using immediate tube withdrawal and temporary subconjunctival tube placement | Mitsui N, Narita A, Sugihara K, Okuda S, Ishikawa T, Noso M, Seguchi J, Chihara E | 10th International Congress on Glaucoma Surgery | 2020年2月 ロンドン |
| 自然軽快した特発性uveal effusion syndromeの一例 | 杉原佳恵、瀬口次郎 | 西部勤務医会 | 2019年11月 岡山 |
| Risk factors for corneal endothelial cell loss after implantation of the scleral-fixated intraocular lens | Sugihara K, Seguchi J, Narita A, Okuda S, Mitsui N | 32nd Asia Pacific Association of Cataract & Refractive Surgeons Annual Meeting 2019 | 2019年10月 京都 |
| 自然軽快した解離性眼動脈瘤による圧迫性視神経症の1例 | 奥田 聖瞳、瀬口次郎、杉原佳恵、光井奈瑠香、成田亜希子、伊勢田恵一 | 第57回日本神経眼科学会 | 2019年10月 札幌 |
| 緑内障手術パラダイムシフト | 成田亜希子 | 第60回大阪眼科手術の会 | 2019年10月 大阪 |
| シュレム管の血液充えいパターンとトラベクトーム手術成績との関連についての検討 | 杉原佳恵、成田亜希子、石川智子、奥田聖瞳、光井奈瑠香、能祖美樹、瀬口次郎 | 第30回日本緑内障学会 | 2019年9月 熊本 |
| 強度近視黄斑円孔手術中に発生した上脈絡膜出血の一例 | 杉原佳恵、瀬口次郎、奥田聖瞳、光井奈瑠香、成田亜希子 | 第5回新手術ビデオカンファレンス | 2019年7月 岡山 |
| シュレム管の血液充えいパターンとトラベクトーム手術成績との関連についての検討 | 杉原佳恵、成田亜希子、石川智子、奥田聖瞳、光井奈瑠香、能祖美樹、瀬口次郎、大月洋 | 第65回岡大眼科学教室同門会総会ならびに岡大眼科学教室学術講演会 | 2019年6月 岡山 |
| Impact of phacoemulsification on filtering bleb morphology identified via three-dimensional anterior segment optical coherence tomography | Narita A Miyake T, Sugihara K, Ishikawa T, Ariyasu K, Mitsui N, Seguchi J | 8th World Glaucoma Congress | 2019年3月 メルボルン |
| Evaluation of blood-filling patterns in Schlemm's canal for trabecutome surgery | Sugihara K Narita A, Ishikawa T, Ariyasu K, Mitsui N, Nouso M, Seguchi J | 8th World Glaucoma Congress | 2019年3月 メルボルン |
| Treatment of papillomacular retinoschisis in glaucoma patients with an acquired optic disc pit | Ariyasu K Narita A, Sugihara K, Mitsui N, Ishikawa T, Nouso M, Seguchi J | 8th World Glaucoma Congress | 2019年3月 メルボルン |
| 光線力学療法を行った孤立性脈絡膜血管腫の3例 | 光井奈瑠香 | 第72回日本臨床眼科学会 | 2018年10月 東京 |
| Impact of phacoemulsification on filtering bleb morphology identified via three-dimensional anterior segment optical coherence tomography | Narita A Miyake T, Sugihara K, Ishikawa T, Seguchi J | 9th International Congress on Glaucoma Surgery | 2018年9月 モントリオール |
| 大人の眼のお話 | 瀬口次郎 | 岡山市立操南公民館 教養講座 寿大学 | 2018年9月 岡山 |
| 眼の健康も日々の積み重ね-糖尿病網膜症・加齢黄斑変性から学ぶこと- | 瀬口次郎 | 第8回岡山済生会総合病院市民健康セミナー | 2018年8月 岡山 |
| 緑内障手術最前線 | 成田亜希子 | 第8回岡山済生会総合病院市民健康セミナー | 2018年8月 岡山 |
| やってみよう!眼のセルフチェック | 三宅智恵 | 第8回岡山済生会総合病院市民健康セミナー | 2018年8月 岡山 |
| 緑内障眼にみられた黄斑網膜分離症の2例 | 有安 奏 | 第10回KOST研究会 | 2018年6月 岡山 |
| 白内障手術がトラベクレクトミー術後濾過胞に与える形態学的影響 | 杉原佳恵 | 第64回岡大眼科学教室学術講演会 | 2018年6月 岡山 |
| 見えにくいと感じたら 糖尿病と視力低下 | 瀬口次郎 | 健康フェスタ in Okayama | 2018年5月 岡山 |
| 胎生血管系遺残に起因する硝子体出血術後の視野障害 | 杉原佳恵 瀬口次郎、成田亜希子、能祖美樹 | 第41回日本眼科手術学会学術総会 | 2018年1月 京都 |
| 両眼性の重篤な視力障害を発症したMPO-ANCA陽性肥厚性硬膜炎の1例 | 杉原佳恵 瀬口次郎、能祖美樹、成田亜希子 | 第71回日本臨床眼科学会総会 | 2017年10月 東京 |
| 緑内障-基礎から最新の治療まで- | 成田亜希子 | 神戸薬科大学第41回生涯研修会 | 2017年9月 岡山 |
| 緑内障の最新治療 | 成田亜希子 | 岡山芳泉高校同窓生による市民公開講座2017 | 2017年7月 岡山 |
| 脱臼眼内レンズを用いた強膜内固定の1例 | 杉原佳恵 瀬口次郎、能祖美樹、成田亜希子 | 第3回新・手術ビデオカンファレンス | 2017年7月 岡山 |
| 両眼性の重篤な視力障害を発症したMPO-ANCA陽性肥厚性硬膜炎の1例 | 杉原佳恵 瀬口次郎、能祖美樹、成田亜希子、大月 洋 | 第63回岡大眼科学教室同門会学術講演会 | 2017年7月 岡山 |
| Candida parapsilosisによる遅発性白内障手術後眼内炎の1例 | 杉原佳恵 瀬口次郎、能祖美樹、成田亜希子 | 第9回KOST研究会 | 2017年5月 岡山 |
| 緑内障手術-最近の話題- | 成田亜希子 | 福山眼科セミナー | 2017年4月 福山 |
| 緑内障手術アップデート | 成田亜希子 | ひとみ会 | 2017年2月 広島 |
| ロングチューブシャント手術 -私の経験- | 成田亜希子 | 第7回緑内障チューブシャントの会 | 2016年11月 京都 |
| トラベクトームを用いた流出路再建術の短期術後成績と合併症 | 清水壮洋 成田亜希子、三宅智恵、秋元悦子、能祖美樹、 瀬口次郎、大月 洋 | 第62回岡山大学眼科同門会総会ならびに学術講演会 | 2016年6月 岡山 |
| 緑内障手術アップデート | 成田亜希子 | 津山眼科講演会 | 2016年4月 津山 |
| 最近経験した手術症例 | 成田亜希子 | 第20回五国緑内障ラウンドテーブルディスカッション | 2016年2月 高松 |
2024年07月
眼科
受付時間
(初診)8:00~11:30
(再診)7:30~11:45
(再診)7:30~11:45
外来診療開始
8:30~
※ただし、予約の方、救急の方はこの限りではありません。
各診療科の受付時間をご確認ください
各診療科により受付時間や休診日が異なりますので、正確な時刻は外来診療担当表をご確認ください。
到着確認を行ってください
自動再来受付機による受付だけでは、診察の順番は決定しません。
必ず、受診される診療科窓口にて到着確認を行ってください。




